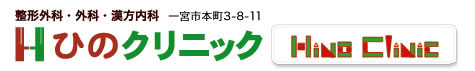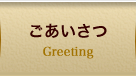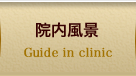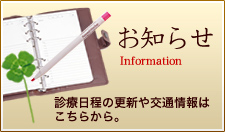「ウソのウソはホントなの?」「裏の裏は表?」。世の中
相反、対立するものはたくさんあります。そもそも二元論
なんて理屈があるくらいですから、全てのものが二分される
のかもしれません。では、その境界は?
漢方にも陰陽、虚実、寒熱など診断の理論として二元論が
採用されています。でもこれはどちらが正しいというもので
はなく、またどちらか一方だけということもないのです。
つまり混在する、併存するものなのですね。ただ単にどちら
寄りなのか、ということです。だから境界も非常に曖昧です。
なぜならどちらか一方があって初めてその反対も成立する
からです。シーソーは両側におもりがあって初めて成り立ち
ますよね。
さて、だからと言って今回は漢方の話ではなかったりします。(笑)
世の中、善悪や男女など二元論で成り立つけど、どちらか
一方では成り立たないと言うことを忘れてないかい?という
話です。つまりシーソーの端っこに立って反対側を罵っている
構図が多いんでないの?反対側がなくなったら真っ先に立場が
なくなるのは自分でしょう?って思いませんか?
政治であれば与党と野党、思想であれば保守と革新、伝統で
あれば正統と異端。これらの論点は双方の差そのものではなくて、
どの辺が相反している境界なのか、なのだと思います。境界を
知ることが双方の存在を可能にするわけですから、境界の位置
こそが論議される価値のあることではないかと思うのです。
両極端な位置からお互いを批判しているのは境界に支配されている、
いわば同じ穴のムジナなのではないかな、と。校則を遵守する
生徒会長と、校則くそったれな不良も校則に支配されている
点で同類なのですね。例えが子供っぽい所はスルーで。(^ ^;)
TPPにしても安保法案にしても、是非を問うても恐らく答えは
出ないでしょう。是と非の間はどこなのか、一歩進んで、なぜ
その境界は生まれたのか、を直視しなければどうも進展しない
ように思います。